みなさんオープンワールドゲームやってますか?
広大なフィールド、圧倒的なグラフィック、そして戦略的なゲームなど。
今でこそ当たり前のようにあるオープンワールドゲームですが、長く遊べるゲームとしてどれを選べば良いのか?そもそも自分に向いているのか?
比較的オープンワールドゲームは値段が高いこともあり、色々と悩むところがあると思います。
私自身もオープンワールドゲームには賛否両論なところもあり、正直”こういう要素があるからオープンワールドゲームは嫌い”と明確な苦手意識すら持っている場合もあります。
今回はそんな膨大なゲーム体験をできるオープンワールドゲームについて紹介したいと思います!
このブログの目次
オープンワールドゲームの良いところ
広大なマップがシームレスに繋がっており、プレイヤーが行きたい場所へ自由に行動できます。
敵の配置や地形を活かして攻略法を考える「戦略性の高さ」も、オープンワールドならではです。
戦略的なプレイができる
まずオープンワールドということは、前提としてマップが広いです。
全ての町やフィールドがシームレスに繋がっており、自分が行きたいところには基本的に行けるようになっています。
そのため、好きな場所へ好きなタイミングでいき、好きなように敵を倒せるといった戦略的な行動ができるようになります。
作りこみがしっかりとされているゲームでは、フィールドギミックを駆使した計画的な攻略を考えることができ、無限の遊び方ができるゲームもあります。
サイドクエストが豊富
メインストーリー以外にも、地域ごとのサブイベントや隠しボスなどが用意されています。
寄り道を楽しめる自由さがあり、「やってもやらなくてもいい」設計が長く遊べる理由です。
ファストトラベルで快適に移動
広いマップでも、拠点や主要地点に一瞬で移動できるファストトラベル機能のおかげで、テンポよく遊べます。
これにより必須ではないサイドクエストもやる気を持つことができ、普段寄り道をしない人でもなんとなくやってみようかなと思える設計になっています。
リアルで没入感のある体験
シームレスな移動と細かな世界描写が、現実のような体験を可能にしています。
「生きている世界を探索する」感覚を味わえるのは、オープンワールド最大の魅力でしょう。
また、マップの範囲が決まっており、移動のたびにロードを挟んでいたゲームがシームレスに繋がったマップへと進化し、世界への没入感が増しゲーム体験が大きく変わります。
オープンワールドの気になる点
様々な特徴を持つオープンワールドゲームですが、欠点があります。
そして多くのオープンワールドゲームの場合、その欠点はある意味必須の要素にもなっています。
私の体感上、どんなに面白いゲームでも共通してつまらないと感じる部分がありました。
マップの作り込みに差がある
タイトルによっては「広いだけで中身がない」ケースもあります。
最新作では改善が進んでいますが、広さと密度のバランスが難しいジャンルです。
2025年現在では、オープンワールドが行き着くべきクオリティを兼ね備えたゲームは多いですが、それでも作り込みの甘さやリアリティに欠ける部分が目立つ場合もあります。
収集系クエストが単調になりやすい
膨大なフィールドを移動して素材を集めるタイプのサイドクエストは、作業感が出やすいです。
プレイヤーによっては「やらされている」と感じてしまうことも。
そもそも収集する必要がないものまでやり込みとしてやらなければならないこともあり、不要なものあまり役に立たないものがそこら中にあったりで意味を感じないものも多いです。
周回プレイがしづらい
マップが広くボリュームが多い分、2周目以降はテンポが悪く感じる場合があります。
ストーリー性が強いゲームほど、再プレイのハードルは高くなりがちです。
とにかく長い!広い!!
合わないゲームジャンルもある
すべてのゲームがオープンワールドに向いているわけではありません。
一本道のRPGやテンポを重視するタイトルでは、逆に自由度が邪魔になることもあります。
続編で一度オープンワールドが出てしまうと、もう前の仕様には戻らないんじゃないかと思ってしまうよね。
そういえば今のところそういうゲームはプレイしたことないな。
特におすすめのオープンワールド作品
ここからは様々なオープンワールドゲームをプレイしてきた私が、最後まで楽しく遊べたゲームを紹介します!
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド(Switch、Switch2)
今自由度と完成度の高さで、オープンワールドの基準を変えた名作。
ストーリーを語りすぎない構成や地形ごとの工夫が、冒険の没入感を高めています。
語らないストーリーがオープンワールドと相性が良い
オープンワールドの弱点として、自由に行動できるからこそストーリーを放置してサブクエストをこなしてしまったりと今の展開を無視して行動できてしまうなど、没入感に欠ける行動を選べてしまいますが、そもそもあまり語らないストーリーだからこそ、自由に行動できることのメリットをよく引き出せてます。
最初から主人公=強いが定着しているとプレイヤー視点からするとなんか申し訳なくなるんだよね。
わかる。熱いストーリー展開なのに即座にボコボコにされたりすると没入感めちゃくちゃ損なわれてなんか気まずくなる笑
意味のないマップやフィールドが存在しない
オープンワールドなのでもちろん移動時間は長いのですが、そこら中に塔や洞窟、敵の拠点、祠がありとにかく情報量が異常です。
膨大なマップという”膨大”を確かな量と質で実現した数少ない神ゲーだと思います。
とりあえず用意した無駄な地形やリアルは存在せず、プレイヤーが意味を持って渡る谷や登る山。
苦労の末に登った山の上にいるコログ、意外な場所に隠されている祠などプレイヤーの好奇心と期待に応えてくれる行動分析は圧巻です。
戦闘が楽しい
戦闘の抑揚、バランスがちょうど良いです。
BGMも相まって敵の行動やプレイヤーの行動によってBGMが変化して盛り上がってくれるので、その気にさせてくるんですよね。
技術のある人であれば、複数の敵との戦闘を選ぶこともできますし、一匹ずつ誘き出して敵の死角で戦うこともできます。
敵も雑魚敵の中でも上位互換の色違い、ライネルといった最強格の敵も点在し、自分の腕試しで挑んでみても楽しいですし戦闘スキルが磨き上がった後に最初からゲームをプレイすると、元々のリンクの強さを再現するような形で攻略もできるので周回プレイおすすめです。
戦略性の高すぎる敵との戦闘
プレイヤーが思いついたこと全てを実現できてしまう戦闘にも圧巻です。
もうここまで”できること”に特化したゲームは存在してないんじゃないかってくらいなんでもできます。
『なんでもできるから飽きやすい』と『なんでもできるから好奇心を持って試せる』の境界がしっかりとされており、この『この地形だったらあの爆発物や岩使えるな』とか、『オクタ風船使ったら拠点の上まで登って上から弓矢で倒せる…?』など本当に戦略性において飽きがきません。
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと相性が良い人
- 広大なオープンワールドを楽しみたい
- 量より質、質より量どちらも満たしたい
- 硬派なストーリー展開を求めている
- 制限のない自由なストーリーを体験したい
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと相性が悪い人
- 分かりやすいストーリーを体験したい
- 行き先を指示されて行動したい
- 選択が自由すぎるゲームをしたくない
- 戦略的な戦闘が苦手
エルデンリング / ELDEN RING(PS4、PS5、Steam、Xbox)
ダークソウルシリーズやブラッドボーンなどの過去作の要素を取り入れた完全新作です。
オープンワールド(正確にはオープンフィールド)を採用した本作では、プレイヤーが求めている達成感を圧倒的に満たしたフロム史上最高峰の完成度を誇る作品です。
高難易度+オープンワールドの相性の良さ
正直、発売前は不安でした。
ソウルシリーズといえば道中も難しく、ボスを倒すために難しい道をいかに自分の力量で攻略していくかを楽しむゲームだったため、オープンワールドにしてしまったらわざわざ死ぬリスクを背負ってまで雑魚敵と戦う価値を失ってしまうのでは?と。
しかし、そんな不安もしっかりと計算されており、そもそもボスが強すぎるので雑魚敵と戦う必要性が出てきます。笑
でもそれってボスも雑魚敵も死にまくって何もできなくなるんじゃ?と思いますが、簡単に倒しに行けますし、簡単に逃げることもできます。
勝てなくて諦めなくても攻略サイトを見て楽しめる
ソウルシリーズ全般に言えますが、難しく途中で挫折してしまう人は多いんじゃないかと思います。
しかし、今作はとにかく一度折れそうになったら攻略サイトを見てしまうことをお勧めします。
相棒となる馬(?)のトレントが優秀すぎるため、対象となる敵を倒したらすぐさま逃げてしまえば良いですし、自分が攻略できそうな場所を選んで進むことができます。
それゆえに攻略サイトを見て欲しい武器だけを先に取りに行ってしまったりもできます。
むしろあまりにもコンテンツが多いので攻略サイト見た方がいいですよ。
独特の世界観で探索する楽しさ
過去作の中でも特にグロく、血や腐敗の存在が結構重要な要素になっています。
ブラッドボーンも血がテーマでしたが、今作ではさらにグロテスクに表現されています。
というよりもブラッドボーンの設定もある程度取り入れているんだと思います。
そんな残酷な世界観を生き延びていくわけですから、とにかくSAN値が削られていきます。
”広大なフィールド”に伴う弱点、”作り込みの甘さ”はエルデンリングには存在しません。
前述したゼルダ同様に、作り込みに妥協はなく、むしろこれでもかというほど細部までこだわりを持って構成されたマップは本当に驚きます。
従来通り、NPCイベントもたくさんありフラグ回収するのはとても大変ですが、世界観を知る鍵を持った人物も多く、全てがポジティブには終わりませんがストーリー進行上知っておくと楽しいです。
周回プレイが楽しくなる要素が多い
周回プレイを検討する際は前述の通り、攻略サイトを見ることの意味が生きてきます。
初見の時には気づけなかった武器や魔法、イベントやボスなど、ある程度スキルが身についた2週目以降だからこそもう一度遊びたくなった時でも、新しい気持ちで挑むことができます。
1週目では放浪騎士を選んだ人でも、2週目では星見を選んで魔法を中心としたビルド・戦闘を行うなど、幅広い遊び方を選択できます。
私は最初は星見で魔法剣士、2周目も囚人を選んだのに結局魔法剣士になりました。
エルデンリングと相性が良い人
- 高難易度のゲームがしたい
- オープンワールドに無限の可能性を求めている
- ビルドを変えて周回プレイしたい
- 硬派なゲーム体験をしたい
- ソウルシリーズ、ブラッドボーンが好き
エルデンリングと相性が悪い人
- 特に壁がなくスムーズにゲームを進行したい
- 難しいシステムのゲームが嫌い
- グロテスクな世界のゲームが嫌い
- マップに迷いやすい人、探すのが苦手
- 暗い、狭い洞窟が怖い
サイバーパンク2077(Steam、PS4、PS5、Xbox、Nintendo Switch 2、macOS)
これまで紹介した中でも、最も密度の濃いオープンワールドを実現したのがサイバーパンク2077です。
世界観はやや癖があるため、好き嫌いは分かれる作品ですが、圧倒的な情報量、世界への没入感を求めるのであればこのゲーム一択です。
もはやデジタルで人生を送れる規模の作り込み
PS5で発売された当初は、夜にお酒を飲みながらこの世界に完全に自分自身を入り込ませて遊んでました。
そのくらい街並みのクオリティが高く、与えられる選択肢が多いため、自由に行動して遊ぶことの意味を作り上げたゲームだと思います。
グラフィックはもちろん、人一人の挙動があまりにもリアルです。
ただ適当に街を歩いているだけでも、”生きている人たち”を実感できますし、主人公Vを通して行きつけの店で買い物をしたり、仲間とコミュニケーションをとることで新しい依頼につながり、ギャングたちと仲良くなることで、主人公になりきって裏社会での立ち位置を築き上げていくことができます。
こだわり抜かれたリアルなコミュニケーション
例えば車やバイクを運転している時に、クエストの依頼や仲間から電話がかかってくることがあります。
しかし、車両事故や敵からの襲撃などやむを得ない状況になると、電話は中断され、問題を解決した後にしっかりと話が途中から続いたりと結構リアルです。
また、プレイヤーの動きや成果に合わせて色々な人から電話がかかってくるようになり、実績を積んでいきその評判を聞きつけたギャングから新しい依頼を受ける。
そういった流れが、ゲームとしてではなく実際に裏社会を生きていくことのリアルさを表現されており自分の行動が与えるゲーム(=世界)へのアプローチがしっかり反映されているのが嬉しいですね。
世界観に合ったビルドによりVの生き方を選べる
サイバーパンク2077では、ネットランナー、サンデヴィスタン、刀、銃特化など様々なビルドが可能です。
しかもよくあるゲーム的なビルド(ステータス依存による選択)ではなく、世界観にあったビルドを行うことができ、その世界のエキスパートとしてビルドを選択することになります。
特化させたいビルドが決まっても、ある程度ビルドの仕方(スキルポイントの振り方)は決まっており、器用貧乏的な成長は得意ではないゲームですが、ステータス強化をして成長を実感できると莫大なダメージを与えられたり爽快感がすごいです。
専門用語が多いので、ある程度の知識は公式サイトやYoutubeで学ぶのがいいかと思います。
ネットランナーとか度々本編でも出てくる用語で、このゲームにしかない特徴でビルドを通して世界観に浸れますよ!
サイバーパンク2077と相性が良い人
- 世界観まるごと入り込みたい
- 難しい用語も含めて独自のオープンワールドがやりたい
- サイバーパンクな世界が好き
- 主人公の葛藤や生き様を体験したい
- 裏社会的な業界の頂点に立ちたい
サイバーパンク2077と相性が悪い人
- 裏社会的な世界が苦手
- 激しい暴力シーンが苦手
- R18的(性的)表現が苦手
- サイバーパンクな世界が好きじゃない
- ある程度決められたビルドより自由さを求めている
【まとめ】オープンワールドゲームは向き不向きもあるが面白い!
今回はオープンワールドゲームの良いところと正直つまらないところとして、その特徴を紹介してきました!
確かにオープンワールドはこれまでのゲームのスタイルや好みの傾向により、向き不向きがはっきりとしているかもしれませんが、今後も性能が上がったゲーム機にとっても、ゲームのジャンルとしてもしばらくブームが去ることはないと思っています。
年々進化するゲーム機のグラフィック性能や処理能力で、今後も名作と呼べるゲームが誕生することを楽しみにしています!

最新のブログ



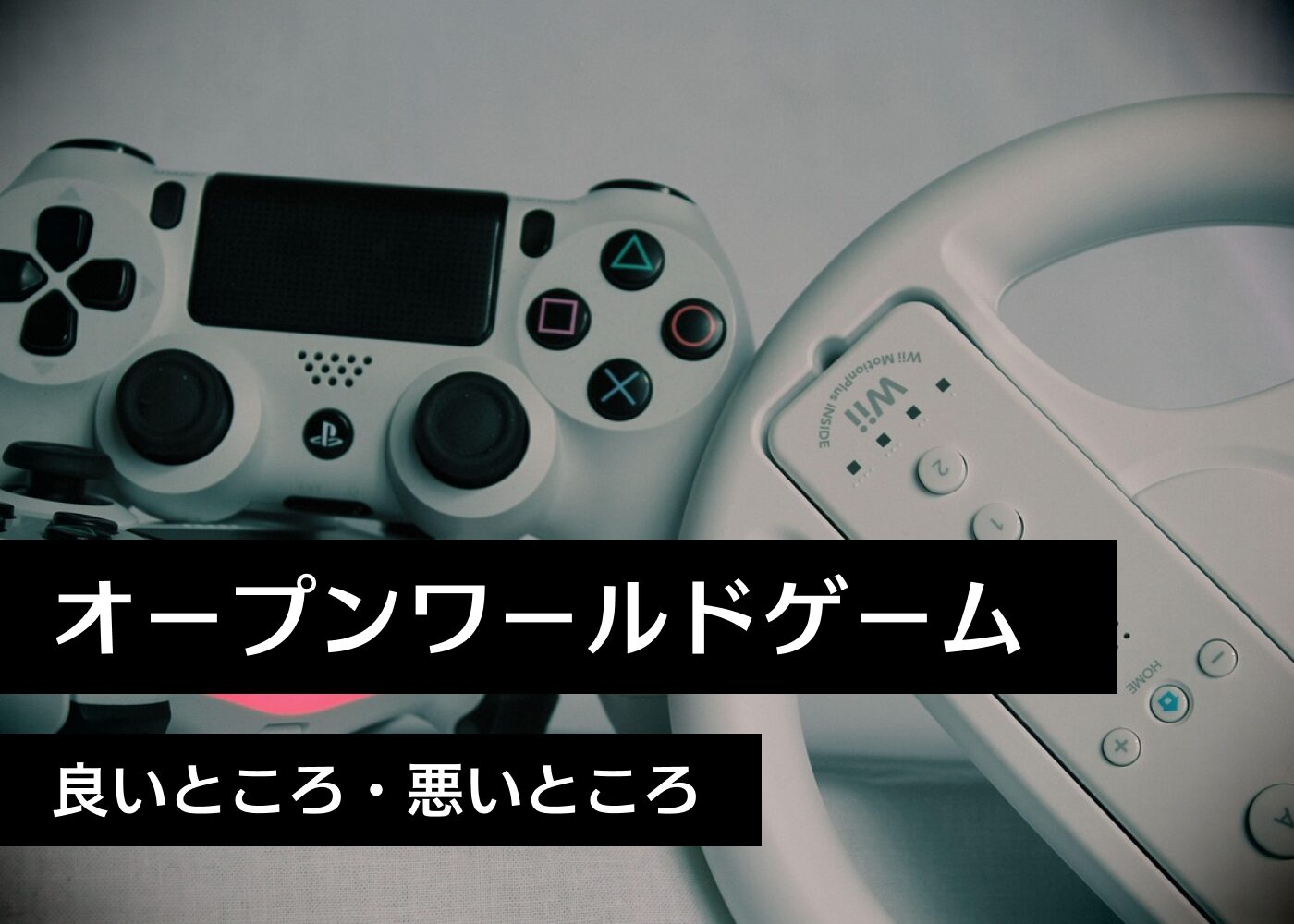




※コメントは最大500文字、5回まで送信できます