最近のゲームはとにかくクオリティが高く、フォトリアルかつ壮大な映像グラフィックのゲームが当たり前になっています。
ゲームの正当な進化としてゲーマーにとっては嬉しい限りですが、一方で昔に比べて『ゲームがつまらなくなった、飽きやすくなった』という意見も多数あります。
今回はそんなつまらない・飽きやすいと感じてしまうゲームがどういうものなのか、またその理由についてゲーム歴25年の私が分析してみたいと思います。
※一部実際のゲームの演出やゲーム性に批判的な意見もありますが、個人の感想のためご了承ください。
このブログの目次
自由なプレイスタイルのゲームが増えすぎた
数年前にオープンワールドというジャンルのゲームが急激に人気を博し、自由なプレイスタイルを特徴としたこのジャンルは、新規ゲームに関わらずシリーズの続編としても、当たり前のように採用されています。
しかし、このシステムを含め自由なプレイスタイルを採用するゲームには大きな欠点があります。
自由と見せかけた不自由さ
この自由なプレイスタイルでゲームを進行できることを”自由”と仮定したときに発生するのが、自由な攻略をしたところで終着点は何も変わらない問題です。
攻略順路を自由に組めたとしても、攻略するためには”指定された場所”に行かなければなりません。
つまり、何も自由なんてものはないんです。
かえって攻略をする順路をプレイヤー側が能動的に選ばなければならない手間ばかりがかかってしまいます。
移動も含めてマップを確認しながら行き先へ向かうので『やらされてる感』しか残らないんです。
世界観の没入感はあるけど、面倒に感じるという弊害もたくさんあります。
自由の本質とは?
では、あえて一本道のゲームを例に挙げてみたいと思います。
ドラクエシリーズや、ファイナルファンタジーシリーズは特に一本道ゲームを代表するRPGですが、作品自体の評価は大変高く、どのシリーズも今でも語り継がれる名作です。
もちろん、好みは人それぞれですがどの作品も何十週もプレイしているほどでした。
一本道だとしても、これらのゲームは攻略をするための戦略を考えければなりません。
- レベルを上げる
- 武器や防具などの新調、改造、強化
- 特定の敵に対する対策をしなければならない
- 強大な敵との戦闘準備
これらの作品に共通していることは、攻略をする上でプレイヤー自身が『考えながら』選択するということです。
しかもそれをやれと言わんばかりに用意されているのではなく、プレイヤーの知識を使って攻略方法を考えるということです。
もちろん選択をしなくてもクリアできますが、それ相応の困難な道を乗り越えていく必要があります。
似たような展開、ゲーム的システムの弊害
特にオープンワールドでは顕著なのですが、ゲームを進行する上で『お決まりの展開』が目立ちます。
①目的地に着く→②ムービー→③行動→④ムービー→⑤解決→①目的地に向かう
基本的にはこれの繰り返しなんです。
ゲーム上で与えられた攻略方法の手順が選べるようになった弊害として、目的を達成した時の辻褄を合わせる必要性があります。
常に平行線上にストーリーが展開され、同時に進めることができるからこそ、『主軸となるストーリー』は、全ての展開を達成するまで進めることができなくなってしまいます。
つまらなそうなストーリーも結局やらされる
自由な選択肢を与えられても、サブクエストやメインクエストでも、なんとなくつまらなそうでやりたくないものってあるんです。
しかし、ゲームの性質上重要な武器やアイテムを手に入れるためには結局プレイヤーには選択権がなかったりなど矛盾が生じます。
結局のところ一本道と大差がないんです。
ただ面倒になっただけ?
プレイヤーに”自由に”ゲームをさせない
仕事が終わり息抜きにゲームをやろう!と思っても気づけばコントローラーを置いている時間の方が長い一日で終わってしまったなんてことありませんか?
最近のゲームではフォトリアルなため、映像を魅せるゲームが増えたことにより、フォトモードの実装は必須な要素になりつつあります。
フォトモード、ゲーム性と満足感にしか興味ない私にとっては、非常に複雑な気持ちになる存在です。
そして気づけば長いムービー。
目的地にたどり着いたらムービー。
少し動いたら即ムービー。
フォトモードで撮ってSNSでアップしてくれと言わんばかりの演出だらけですね。
ムービー過多、フォトリアル化で失敗したゲーム例
キングダムハーツIII
キングダムハーツといえばあまりにも広大な伏線、外伝シリーズの多さで有名ですが、ディズニーやFFとのコラボで日本国内外問わず圧倒的な人気タイトルでした。
私自身、相当やりこんでおそらく80%くらいはゲームの全容を把握しているであろうこの名作も、キングダムハーツIIIの登場で一気にテンションが下がってしまった異例の作品です。
何よりも世界観とキャラの見た目が合っていない。
リアルにするべき挙動とそうではない挙動の塩梅が取れておらず、シリアスな展開とギャグのシーンが多い本作はあまりにも違和感があります。
そして長いムービー、操作時間の方が短いんじゃないかというくらい長い。
キングダムハーツIIくらいの規模とグラフィックであれば大成功したであろう作品。
ムービーにリソースを割きすぎて肝心のゲームプレイの質の低下や、伏線だらけの神ストーリーにトドメをさしてしまった最後の展開など、ゲームプレイより世界観の魅せ方を優先してしまった例ですね。
FF16(ファイナルファンタジーXVI)
PS5専売としてスクエニの本気が垣間見える…はずだったFF最新作です。
とにかくムービー!長すぎる!
あと、無駄に派手なエフェクト演出や似たり寄ったりな残虐シーン(とりあえずスローモーションで斧がブッ刺さる、足で蹴って人をひっくり返す)など、やはり違和感しかない演出が多い印象でした。
リアルにすればするほどリアルじゃない部分(ゲーム的な演出)が目立つようになり、ゲームである意味がなくなってしまうんです。
余談ですが、とりあえず適当にボタン押しとけばクリアできてしまうように作られているのは、ゲームとしていかがなものだろうか。もったいない!
リアルな作風だからこそ目立つシュールさ
いくつか例を挙げてみます。
Ghost of Tsushima / Ghost of Yotei
まず、この2つは神ゲーであることは間違いありません。
オープンワールドでありつつも、圧倒的なクオリティとプレイヤーの興味を引くストーリー、そして前述したムービーも最小限となっており、プレイヤー目線でよく考えられたゲームです。
リアルゆえの最大の敵、ゲームシステム
あまり気にするところではないのですが、フォトリアルかつ高グラフィックゲームがとにかくゲーム的な要因が目立ちます。
例えば、狐を追いかける要素や、狼との共闘クエスト、一騎打ちの演出など。
それぞれ場所やセリフなどは若干変わるもの、演出自体は一貫して全く同じものになります。
- ①拠点に行く
- ②対象の人物(動物)がいる
- ③毎回同じカットシーンが入る(一騎打ち)
- ④毎回同じ目的を達成する(戦闘、祠に向かうなど)
強制ムービーで行うシーンは毎回違うんは当然ですが、サイドクエストは同じシーンだらけです。
どうしても『あぁ、またこの演出ね』となってしまいます。
なので慣れてきた頃には飽きてしまいますし、シュールなので飛ばしたくなってしまいます。
DEATH STRANDING / DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
コジマプロダクションのゲームは、そもそも開発者が言及している通り作りたいものを作っているので書くかどうか悩んだのですが、前作デスストが良かっただけにどうしても評価したくなったので書きます。
正直、シュールの極みといいいますか、フォトリアル以前にもはや本人レベルのグラフィックなので、もうゲームキャラを操作しているんじゃなくて、俳優を操作しているに近いです。
ですが、ゴーストオブシリーズ同様に同じ演出があまりにもくどすぎました。
そしていかんせんムービー過多を極め尽くした演出。
ゲーム的に仕方のないシェルターの人々のホログラムなど。
唯一無二かつ、コジマ監督にしかできないゲームであることなど、これだけで評価をするのは申し訳ないのですが私はギブアップでした。
多くのプレイヤーがゲームに求めていることとは
今でこそゲームのジャンルは膨大に存在し、数年前とは比べ物にならないくらい選択肢の幅が広がっていますが、そもそもプレイヤーはゲームに何を求めているのでしょうか。
リアルなグラフィックのゲームは特段求めてない?
そもそも根本的な話ですが、いつからプレイヤーはグラフィックを求めたのでしょうか?
きっと映像技術が上がったことにより、ゲーム開発者側で勝手に始まり、評価を受けると同時に業界で当たり前になってしまったんだと思います。
今でもリアルなグラフィックをアピールするゲームは多く、初見では多くのユーザーはポジティブな評価をしていますが、実際にプレイをして満足感を得ているゲームって全然真逆の性質を持ったものだったりします。
むしろ、グラフィック推しのゲームほどコケるジンクスさえあります。
リアルな現実よりも非現実を
ここではあまり書きませんが、政治的情勢を取り入れる流れ(いわゆるポリコレ)や、現実の要素を入れた(キングダムハーツIIIのSNS画面)作品は基本的に失敗しています。
ゲームに取り入れても良い現実の要素は、町並みだったり社会性だったりだけでよく、そういった現実では絶対に体験できない要素こそ、ゲームで遊ぶ価値のあるものだと考えています。
ゲームというのは非現実な体験を、現実のプレイヤーの代わりにゲームの中の主人公が体験するものです。
これはファミコンでもプレステ1時代から一貫して変わっておらず、時代と共にグラフィックやシステムが進化を遂げているのでありこのゲームの構造自体は変わっておりません。
受動的な攻略から能動的な攻略へ
最近のゲームは与えられた攻略法を辿るものが増え、自分で調べて試していく楽しさが得られる機会が減ってしまったと思います。
いつからゲームはプレイヤーが能動的に攻略するものから、用意された攻略法を辿るようになってしまったのでしょうか。
ゲームプレイを楽しむよりも、キャラクターのストーリーや心情を見せすぎな気がしますね。
規模よりも重厚なゲーム体験を
“広大な”を謳っている作品は数多くありますが、正直なところデメリットの方が多く感じます。
- 移動の不便さ
- 目的地への強引な誘導
- ファストトラベルによる能動的な移動の存在意義
フィールドが広大だともはや移動すること、ファストトラベルすら面倒だと感じるようになってしまいます。
一つの拠点でストーリーを楽しんだ後に次の目的地で新しいストーリーが発生するよりも、地続きでストーリーが展開されており、その上で自分なりに攻略法を探しに自由に移動できる方が楽しい気がします。
【まとめ】今後のゲーム業界に期待
ムービー過多、フォトリアル化が進むゲームで、本来のゲームの楽しみ方が損なわれてしまい、もったいない進化を遂げたシリーズも多々ありました。
技術アピールすることよりも、ユーザー視点で考えられるゲームが今後増えていくことを信じて期待したいと思います!

最新のブログ
-
【PS5・Switch】2025年に買ったゲームで面白かったゲームを紹介!
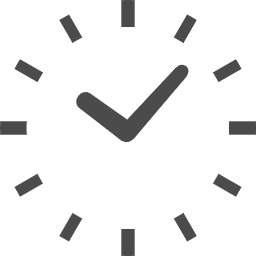
2025.12.09





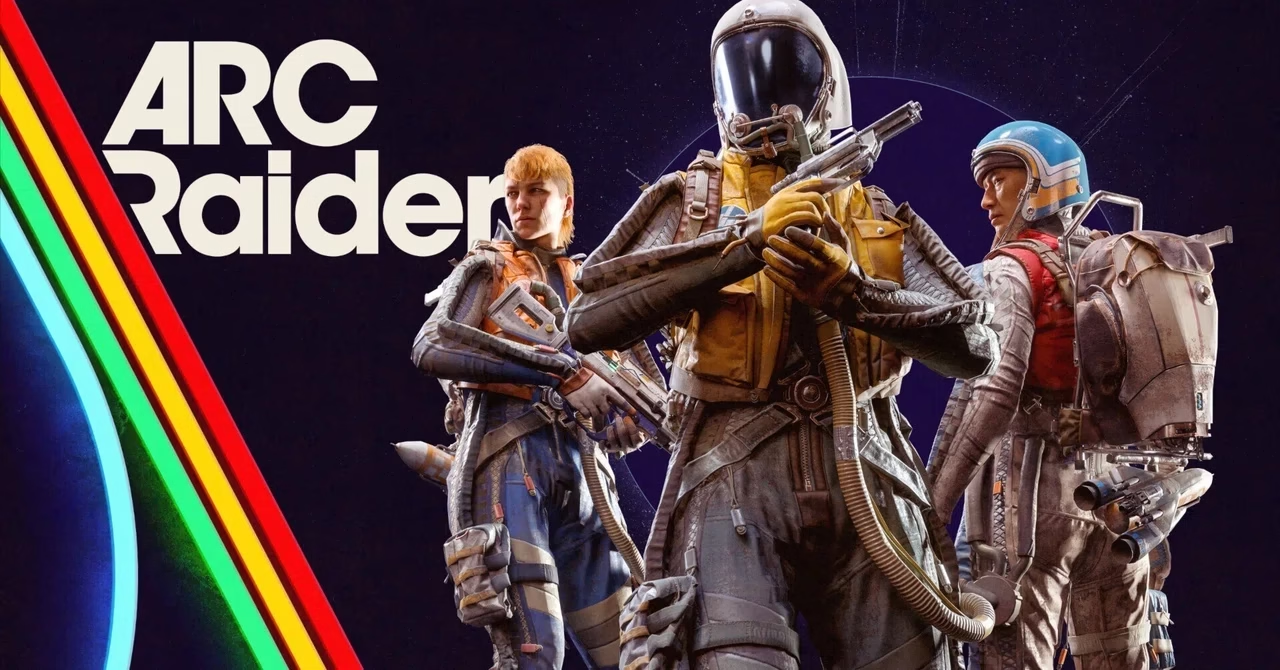

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます